
京都機械工具株式会社(KTC)製品がなぜ、多くのユーザーから高い評価を受けているのか。その要因を知るため、商品開発部の坂根様と頼富様にお話を伺って参りました。
「壊れ方の美学」インタビュー

京都機械工具株式会社
執行役員(T&M 推進本部)TRASAS 開発部、商品開発部担当
坂根 徹様

京都機械工具株式会社
T&M推進本部 商品開発部 汎用開発グループ マネージャー
頼富 士朗様
―― 先ずは主力商材の簡単なご紹介からお願いいたします。
[坂根様 ※以下敬称略] 大きく分けるとハンドツール、自動車の専用工具、ケースを手掛けている、総合工具メーカーです。
その中でも、KTCブランドの位置付けとして、フラッグシップのネプロスと汎用工具、自動車専用工具。これらが、皆様がお使いになられていて、一般的に目にされている商品になります。
開発の立場からすると、汎用工具というものに関して、設計上で精度を詰め、安全安心に使える工具というのが基本コンセプトになっています。
自動車専用工具に関しては、今まで培ってきたノウハウがたくさんあります。そのため、どこにも追従できないものを開発していると思っています。
また、開発にあたって、多くのモニター先に協力していただき、色々なロケーションやシチュエーションで使い勝手の検証をしてもらっています。そして、実際使えるものであるということを「確信をもって」送り出してきました。
――ありがとうございます。お二人のご経歴と、これまで開発されてきた中で思い入れが強い製品についてもお話しいただけますか。
[坂根] 私はずっと開発部門に所属していたというわけではなく、10年間メディカル部門にいた時期もあります。そして、2年前に開発に戻ってきました。
そして、開発の中でも企画側に近い立場です。収納関係やFF WORLD(公式サイト)等、手工具とは違う担当をしてきました。自動車市場寄りの収納が多かったですね。
[頼富様 ※以下敬称略] 最初は坂根と一緒で企画だったのですが、途中からOEMの仕事をずっと受けさせていただいておりました。
専用工具をいくつか担当したこともあります。例えば、自動車のLLCを注入する工具をほぼ1から設計したこともあります。
―― 1からですか。苦労された点も多いのではないでしょうか。
[頼富] たくさんありましたね。元々は、LLCチャージャーにワイヤーの機種というものがありました。ワイヤーが心臓部に当たり電圧するユニットなのですが、車のLLCをドレンから抜き、そのあとラジエーター内の圧力を抜いてやってから、バレルを切り替えることにより、LLCが流れ込んでいくというものになっています。
ここの減圧するユニットが最初の機種では購入品でした。そして、ここがコストウェイトを占めていて、チーム内でも「高いな、安くできないかな」と話し合っていました。
その後、タンクを交換できないかといった話も出てきて、ではやってみようかとなった時に「はい、エジェクタユニットを設計してみます」と言ってしまったんです。それがほぼ1から作ることになったきっかけですね。これまでやったことがなかったのですが、色々やってみたいという思いもありました。
そして、元々買っていた既製品のユニットをぶった切って寸法を測り、それをコピーして作ってみたはいいけど性能がでないということもありました。最終的には、どこがこの研究をしているんだろうと辿って行きました。すると、ある大学に減圧ユニットの研究をしている先生がいたので、連絡をとって色々と見せてもらうことができました。そこでは、「どこがどうなれば、どのような性能が出るようになるか」まで、こと細かに教えていただけました。
そして、学んだことを元に実験を繰り返し、ようやく最適な形状を設計できたという製品になります。
このように、我々としても大元のところまで理解してからやりたいという思いが強いので、評価も細かくやっています。また、昔やっていたからいいアイデアというわけではありません。今開発している別商品でも、「昔やっていたここはあまりうまく機能してないよね」というのがあれば、開発側に持ち帰って、昔の資料を全部ひっくりかえして「ここじゃないか?」と、一からやり直したりもしています。
根幹となるところまで細かく設計しているつもりです。そのため、一個の製品に対して相当な時間がかかってしまうこともよくあります。しかし、そこまで追い込んで完成した製品というものは、市場でもほとんど問題が出ません。だからこそ、安全で安心して使っていただける製品になっています。
緻密に計算された壊れ方
―― 細かい評価とは具体的にどのようなことをされているのでしょうか。
[頼富] 汎用工具でもどこから潰れる、どこから壊れ始めるということまで全て評価しています。昔は、スパナであれば大中小の評価をしていればいいよねとなっていたのですが、今は全部のサイズで行っています。
永久的に使えるものではないので、時間がかかったとしても壊れ方まで追い求めたい。チームとして納得できる”安全なものを世の中に出したい”という想いがあります。
例えば、ネプロスの6.35sqラチェットハンドルはNBR290が基本となり、NBR290L(ロングタイプ)というのが後で展開されました。しかし、NBR290Lの開発段階でヘッドが持たないということが起きてしまいました。元となるNBR290の設計では、もう少し負荷がかかっても大丈夫な設計はしていたのですが、NBR290Lではぎりぎりで引っ掛かってしまい出荷できなくなってしまったのです。結果的に、構造が入っている中の部分の、稜線の形をコンマ何ミリを触るだけで大丈夫だったのですが。
―― コンマ何ミリの世界で、壊れ方まで計算されているのですね。
[頼富] はい。同じように設計をしていっていたとしても、使い方だとか長さだとか、その製品による個々の特徴によって微妙な差で、壊れるポイントが変わってしまいます。
最近の事情までは詳しく知らないのですが、台湾や中国で生産されたものは、壊れる箇所がバラバラだったんです。それは、ギリギリのところで設計されているというわけではなく、コピーして大きくしたり、小さくしたただけの製品が多かったためです。ギアレンチのように構成点数が多いものになると、「ソケットのギアが滑る」「クローが割れる」「本体が割れる」のように、違う壊れ方をしてしまうんです。我々は、最終的にユーザーが怪我しないようにどのように壊れるかという思想があるので、それでは困ります。そういった観点で壊れ方にばらつきが出ないところまで、設計を追求しています。
―― どれくらいの精度で事前の解析やシミュレーションをされているのでしょうか。
[頼富] 単純にコンピュータの性能が上がれば解析の精度も上がるということではありません。実体の試験だけでなく、CAE解析というのを行っているのですが、その解析をするためには条件を入れてやらないといけません。
例えば、複数のパーツを単体ではなく、ひとつにまとめてしまうと完全な剛体になってしまうので”壊れない”と言う結果が出てしまいます。それでは実態にそぐわないので、うまくどのように「歪ませるか」「どっち側にどれぐらいの力を加えるのか」といった、解析の条件を割り出す・作り出すという工程が重要になります。
―― 蓄積されてきた膨大な情報と経験を元に、条件を作られているということですね。
[頼富] はい、それがノウハウですね。AIが出した結果を鵜呑みにはできません。
[坂根] それまで失敗をしたり、思いがけない壊れ方もしてきていますから。
[頼富] 今では社内でも、もっと解析してみないかという雰囲気ができていて、部下が率先して勉強会を開いてくれたりと意識も高まっています。

企画が立ち上がる経緯
―― 企画が立ち上がるきっかけで一番多いのはどのようなパターンでしょうか。
[坂根] お客様に近い営業からの要望というのが一番最初にあります。
それ以外には、モニター先からの情報であったり、海外の情報であったり、常日頃から色々な場所で話を聞いているうちにひらめくこともあります。また、自動車業界が長いということもあり「これはいけるだろ、難しいだろう」といった、ノウハウに基づく直感というのもありますね。
[頼富] 他社はわからないのですが、弊社は自動車整備士をしていた人材が多く働いています。そういった人たちからアイデアが出てくることもありますし、自動車の構造から理解している人間同士なので、話が進めやすいという良さもあります。
――企画が立ち上がってから、開発現場との折り合いはどのようにつけられているでしょうか。
[坂根] 企画はあくまで企画なので、理想論を描いて設計にバトンタッチすることもあります。
第一はお客さんの安全と使い勝手。企画側が一見無茶なことを言ったとしても、それが世の中にとって大切で安全安心なものであれば、設計者は何としても作ろうという姿勢で取り組んでくれます。
逆に、設計側から「これだと安全安心なレベルが下がってしまうよ」というフィードバックも当然あります。
安全安心な製品を生み出そうといった共通意識の中で折り合いをつけていき、納期やコストのバランスも考えながら組み立てていく。その後、モニター先に評価していただいて、最終的に製品化していく流れになります。
―― お互いに譲れないこだわりがぶつかることはありましたか。
[坂根] 企画側には設計できない人間もいるので、寸法上無理なことでもこうしてくれああしてくれという無茶を言ってしまうこともあります。設計側はその要望を具現化しないといけないので、そこでのせめぎ合いはもちろんあります。
[頼富] すごく狭いところにこれだけトルクを掛けたいといわれても、物理的に無理といったケースが多いかと思います。
―― 苦労して開発したアイデアが他社に真似されたということはありますか。
[坂根][頼富] ありますね(笑)
[坂根] 真似された上に、特許を取られたりだとかもありましたね。
手前味噌ですが、KTCが出すものだったら大丈夫じゃないかということで、すぐに追従してくるメーカーさんも中にはいらっしゃるかと思います。
ただし、真似と言いましょうか売れている製品は、それだけ世の中に評価いただいているということなので、業界の大きな流れの中で各メーカーが独自の改良を加えて新しい価値を付けることも当然あります。
時代とともに変化していく製品と技術革新
―― 時代の変化にどのように対応しているのでしょうか。
[坂根] 世の中でアナログだった物がデジタル化しています。それに伴い、使い勝手も含め形そのものがどんどん変わってきています。
工具も時代の流れに合わせて進化していますが、その過程で新鋭のメーカーがこれまでにない製品を生み出していくこともあります。
我々としてもノウハウが蓄積されているとはいえ、知らないことも確かにあります。常に勉強しながら進めていく中で、あのメーカーではこういったことをしているなという気づきを得ることもあります。弊社が何もかも先頭を走っているわけでもなく、その先にある見えないところは情報をとりにいかなければ追いつけません。そこはやはり、先行メーカー様を参考にするというケースはもちろんございます。
[頼富] ネプロスや汎用品に関しては営業部門が最新の情報を持っています。そのため、「他社ではこういうことをしている」といったフィードバックをもらい、技術的にできるかも含め検討します。追い求めているというよりも「そこに行かなければならない」という気持ちかもしれませんね。
―― 様々な情報を調べていくうちに「この技術・構造を使ってみたい」という発想から出来上がった商品はありますか。
[頼富] それは専用工具の方が多いかもしれません。ネプロスもですが、次の機種をどうしてやろうというのは常に探し求めています。
これまで作ってきた製品は、追い求めてきた末に完成したものでもあるので、これ以上何かを引けないことも多いです。その場合、足す・掛けるしかありません。そのため、「コストを上げず、いかにして何を足せば、お客様が喜んでくれるだろう」ということは考えていますね。
それとは別で、例えば、収納具やチェストでも、発売するにあたってタイミングの良い時期がありますよね。タイミングを過ぎてしまうと市場の動きが鈍化してしまうことが。そのため、
「5年経ったので、そろそろやらなくてはいけない時期だな」といった始まり方もあります。そこから改めて「お客様が喜ばれるには何を足せばいいのだろう」と考えるといった流れになることも。
―― チーム内での意見交換は普段から活発に行われているのでしょうか。
チームの中でも、誰が何をするかというのが決まりつつあるのですが、メンバー個々が次はこれをやってやろうかなみたいな種をちょっとずつ持っているんですよね。それをうまく引っ張り出すタイミングや方法を私たちマネージャーが考えています。メンバーには普段から視野を広く持って、いろいろなものを見て欲しいというのは言っています。
[坂根] 自動車専用工具であれば、作業の手順から考えることもよくあります。
オイル交換ひとつにしても、「キャップを外す→ドレンボルトを外す→オイルフィルターを外す」といった一連の作業の流れがあります。その作業の中で、「抜けてるものがないか、あるんだけれどももっとやりやすい方法がないか」を考えたり、「新型機種ができたため付けている位置や使ってる物が違っていないかを調べ、それに適用するものを増やしていく」という考え方です。
このように、自動車専用工具は開発側から増やしていくパターンはよくありますね。車種が増えていく、ガソリン車・ハイブリット車で構造も変わってくるので、それに合わせて足りないものを増やしていくということですね。
EHIME MACHINEオリジナルセットについて
―― 弊社(エヒメマシン)のオリジナルセットの開発に関してお話を伺えるでしょうか。この話を初めて聞かれた時に思われたことはありますか。
[頼富] ついにそこまで手を伸ばされたかと思いましたね(笑)
オリジナルセットを組まれるということで、どのように中身をリストアップされたのかなというのは非常に気になりました。それがエヒメさんのターゲットユーザーということになりますから、興味がありました。
―― 入り組み内容を見られての印象はいかがでしたか。
[頼富]ちょっと僕らができないことをやられてるなとは思いましたね。その選択は弊社のボリュームで見た場合には、やらないだろうなという印象はありました。
―― コンセプトとしてはメーカーがやらないことというのがあります。ギアレンチとコンビネーションが入っているとか。
[坂根] 弊社としてはどうしてもオールマイティーというのを考えます。
[頼富] そういうところでうちの入り組みを使っていただければ、非常にありがたいと思います。コストを考えると、メーカーは重複しないように組みますからね。 でも使い勝手から見ると、"こういう時にはやっぱりギアレンチも欲しいんだろうな"と。
―― 頻繁に使う層(ミリ)のところは厚く色んな物が揃っていて、あんまり使わない層は別の何かでカバーできればいいという発想です。
[頼富]私も車や単車をいじるんですが、やっぱりその時に使う工具は選定しますからね。メインの押さえどころというのは、確かに何種類か持っておくというのはいいと思います。
―― トレーの設計など、苦労されたのではと思うのですが。
[頼富]確かに入れ組みが色々あって、難しいポイントはありましたが、比較的スムーズに行ったと思います。
両開きのケースに切削トレイを入れるのは難しいので、そこは担当の者が知恵を絞って、どういう風に並べるか、どういう風に削ればいいかというのは綿密に考えてやってくれていましたね。
我々は、先ず外身となる収納具をグループ会社で生産しています。そして中身となる汎用工具なり専用工具を持っています。その間を埋めるのが切削トレイと考えているのですが、それも社内で削っています。
1m2mの材料になるのですが、削るプログラムも自社で組んでいます。どういう条件になればそれはでるだとか、できないといったノウハウも社内に全て蓄積しています。そのため、複雑な削り方だとか、どこをどういう風にどこまで追い込んで削れるだとか、全部わかります。
このことが、オリジナルセットのご依頼に上手くはまったかなと思っています。
「外も中も間も、全部KTCで作れますよ。全部、自分のところで掌握していますよ。だから、品質も任せておいてください。仮に何かあっても工場の人間に聞いたら全てわかります。」ということを自信を持って言えます。
ケースはどこかから買ってきて、トレイは中身を渡してそれに合うように削ってもらう、といったレベルのものではありません。とことん追い込んで設計してますから。
今後、差別化しようとすれば、「とにかく安いもの」か「しっかり使えるもの」どちらかに寄っていくことになるのではと思っているのですが。これは、どこの業界の何の製品・サービスでもそうかもしれませんね。
―― 要望をいくつも出させていただく中で、この「すべてが社内で完結する」ことの柔軟性と強みはとても感じました。これからも、よろしくお願いします(笑)本日は貴重なお話をしていただきありがとうございました。
[坂根][頼富] ありがとうございました。
インタビューを終えて
総合ツールメーカーでありながら、グループ会社内で大部分の工程をカバーしていることが、どの製品をとってもKTCらしさを感じられることにつながっているのではないでしょうか。
そして、安全性のため、壊れ方まで精密に計算され尽くした設計思想は、美学とも呼べる水準でした。また、KTCブランドが持つ安心感は、多くのユーザーに使われ、長い年月を経て評価されてきたという実績の結晶だということも、今回の取材で見て取ることができました。
【次回】ネプロスチームの立ち上げ段階から携われてきた方にも、別途インタビューをさせていただきました。ネプロスはどのように誕生したのか、そしてこれまでの製品と何が違うのか。ぜひ、楽しみにお待ちください!
関連記事:KTC開発者インタビュー『ネプロス誕生秘話』
関連記事:KTC開発者インタビュー
『ネプロス誕生秘話』
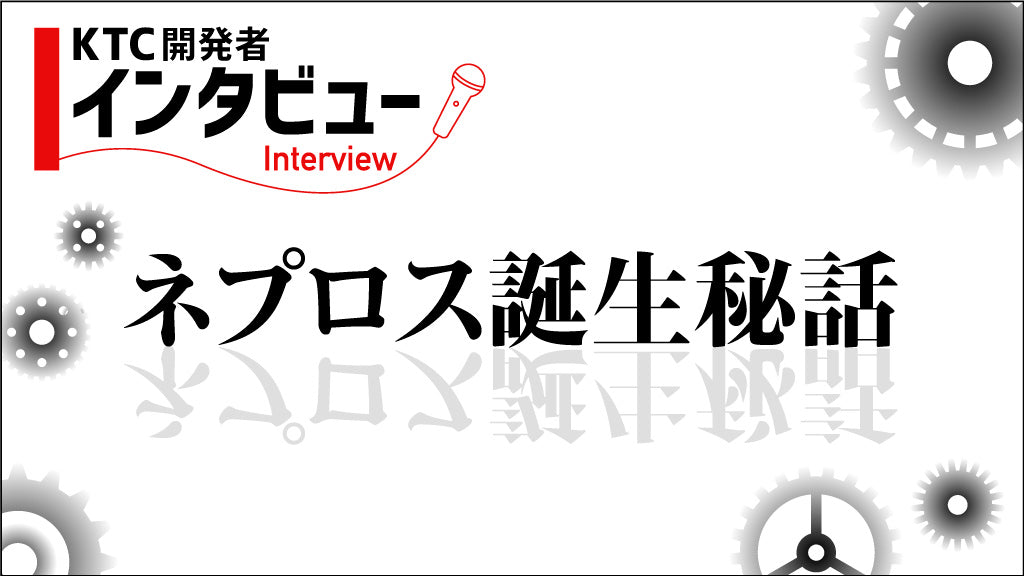
前回のKTCインタビュー「壊れ方の美学」に続き、今回は「ネプロス誕生秘話」をご紹介。チームの中心となり企画段階から開発全般に携われていた商品開発部の寺嶋様から、ネプロス開発の経緯や開発者としての思いなど、ネプロスファン必見のお話を伺って参りました…
View Details














